インターネット利用はメンタルヘルスに悪影響を与えるのか?新たな研究結果とは!?
スマホ疲れを感じてる?📱 デジタルウェルビーイングで健康的なデジタルライフを!👀✨ デトックスやアプリ活用で、集中力アップ、睡眠改善、心身のリフレッシュを実現!
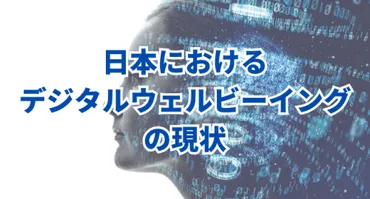
💡 インターネット利用とメンタルヘルスの関係について、新たな研究結果が発表されました。
💡 従来の認識とは異なり、インターネット利用はメンタルヘルスに大きな悪影響を与えない可能性が示されました。
💡 本記事では、具体的な研究内容とその結果について詳しく解説していきます。
それでは、最初の章から見ていきましょう。
デジタルウェルビーイング:健康的なデジタルライフのために
デジタルデバイスを健康的に使うには?
デジタルウェルビーイングが重要
デジタルウェルビーイングは、現代社会において非常に重要な概念ですね。
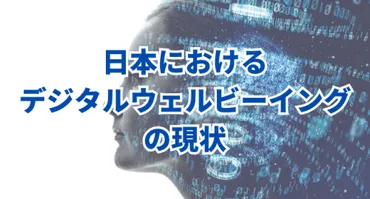
✅ この記事は、デジタルウェルビーイングの重要性を強調し、日本における現状と課題、特にSNS依存や「ながら視聴」などによる心身の健康への悪影響について解説しています。
✅ 具体的な対策として、デジタルデバイスの利用時間管理やデジタルデトックスの必要性を訴え、企業や社会全体が健全なデジタル利用を促進する必要があると主張しています。
✅ さらに、日本の現状ではデジタルウェルビーイングへの取り組みが欧米諸国に比べて遅れていることを指摘し、企業や教育機関が率先してデジタルデトックスやデジタルデバイスの使用ガイドラインを導入する必要性を訴えています。
さらに読む ⇒StartHome出典/画像元: https://home.kingsoft.jp/news/dx/dx_portal/digital-well-being.htmlデジタルデバイスの使い過ぎは、確かに様々な問題を引き起こす可能性がありますね。
デジタルウェルビーイングとは、健康やワークライフバランスを考慮し、デジタルデバイスを適切に活用することを指します。
過度なデジタルデバイス使用は、視力低下、睡眠不足、集中力低下など、身体的・心理的・社会的な問題を引き起こす可能性があります。
デジタルデトックスは、一時的にデバイスから離れることでリフレッシュを図る方法です。
近年、デジタルデバイスの使用頻度が急増しているため、デジタルウェルビーイングは注目を集めています。
デジタルウェルビーイングを実践するには、スマホツールの設定を見直したり、専用のアプリを利用したり、デジタルデトックスを実践したりするなどの方法があります。
なるほど、デジタルウェルビーイングは、健康的なデジタルライフを送る上で欠かせないものですね。
デジタルウェルビーイングへの関心の高まりと課題
スマホ使いすぎ? 日本のデジタルウェルビーイング意識は?
他国より低い
デジタルウェルビーイングは、個人だけでなく企業にとっても重要な課題ですね。

✅ デジタルウェルビーイングは、スマホの使いすぎによる心身の不調からユーザーを解放し、健康で幸せな状態を促進することを目的とした考え方です。2018年にGoogleとAppleが相次いでデジタルウェルビーイング機能を発表したことが、この考え方の注目を高めました。
✅ デジタルウェルビーイングが重要視される背景には、スマホ中毒による健康被害や生産性低下などの問題がある一方で、企業にとってもユーザーがスマホから離れてしまうことによる損失を防ぐというメリットがあるからです。
✅ GoogleとAppleは、スマホの使用状況を可視化したり、アプリの使用時間を制限したり、夜間の通知を制限したりするなどのデジタルウェルビーイング機能を搭載しています。これらの機能により、ユーザーは自分のスマホの使い方を見直し、より健康的なデジタルライフを実現できるようになります。
さらに読む ⇒ビジョンイズム出典/画像元: https://www.vision-net.co.jp/morebiz/digital_well-beingスマホの使用状況を可視化したり、アプリの使用時間を制限したりできる機能は便利ですね。
スマートフォンやタブレットの普及とコロナ禍でのテクノロジーへの依存により、デジタルウェルビーイングはますます重要視されています。
GoogleやAppleなどのIT企業は、デジタルウェルビーイングの重要性を認識し、スマートフォンなどのデバイスにデジタルウェルビーイング機能を搭載しています。
しかし、日本のデジタル機器使用者は、他国に比べて使いすぎているという意識が低く、利用を制限しようとする人が少ないようです。
確かに、スマホの使い過ぎは問題ですが、デジタルウェルビーイング機能は有効な対策となりそうですね。
デジタル機器の使い過ぎとメンタルヘルス:新たな知見
デジタル機器はメンタルヘルスに悪影響?
統計的に裏付けなし
デジタル依存に関する議論は、近年ますます活発化していますね。
公開日:2019/03/14

✅ 1995年、精神科医イヴァン・ゴールドバーグはインターネット依存症について冗談半分に投稿したところ、多くの精神科医が真剣に受け止め、ネット依存者のためのオンラインサポートグループが設立されました。しかし、ゴールドバーグは依存という言葉の使用に懸念を示し、「病的なインターネット利用障害」と名称を変更しました。
✅ 近年、スクリーンタイムの悪影響に対する社会的不安が高まっており、多くの専門家やメディアが「デジタル依存」や「メンタルヘルスの危機」といった言葉を使い、スクリーンタイムの制限を促しています。しかし、専門家の中には、スクリーンタイムそのものよりも、その内容や使い方に注目すべきだとする意見も出ています。
✅ 2018年以降、デジタル依存に関する議論は新たな局面を迎え、フェイスブックやアップルなどのテック企業は、ユーザーのデジタルウェルビーイングを支援するための取り組みを始めました。具体的には、ユーザーが自分のデヴァイス利用習慣を監視できるツールを提供したり、アプリ内での時間管理機能を導入したりしています。これらの動きは、テック企業がデジタル依存問題に対する懸念を認識し、対応を始めたことを示唆しています。
さらに読む ⇒WIRED.jp出典/画像元: https://wired.jp/2019/03/14/tech-addiction-debate-all-wrong/スクリーンタイムそのものよりも、その内容や使い方に注目すべきという意見は興味深いですね。
デジタル機器の使いすぎは、睡眠の質の低下、眼精疲労、視力の低下、インターネット中毒など、様々な弊害をもたらす可能性があります。
そのため、デジタルウェルビーイングの実践が重要視されています。
しかし、最近の研究では、インターネット利用が心理的ウェルビーイングやメンタルヘルスに悪影響を与えるという一般的な考えは、統計的に裏付けられないことが示されました。
デジタル依存は深刻な問題ですが、テック企業が対応を始めたのは良い兆候ですね。
インターネット利用とメンタルヘルスの関係:大規模データ分析の結果
インターネット利用は心の健康に影響するの?
影響なし
インターネット利用はメンタルヘルスに悪影響を与えないという結果は、驚きですね。
公開日:2024/05/17

✅ ネットサーフィンはメンタルヘルスに悪影響を与えるという一般的な認識とは裏腹に、新しい研究結果では、インターネットの使用は心理的ウェルビーイングやメンタルヘルスに大きな脅威を与えないことが判明しました。
✅ この研究は、世界各国の数百万人の心理的ウェルビーイングやメンタルヘルスと、各国のインターネット利用状況を比較分析したもので、168カ国、243万人を対象とした調査データに基づいています。
✅ 研究結果から、インターネット利用と心理的ウェルビーイングやメンタルヘルスの間に直接的な因果関係は認められず、インターネットへのアクセスが増加しても、個人の幸福度やメンタルヘルスに悪影響は及ぼさないことが明らかになりました。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/premier/health/articles/20240315/med/00m/070/001000d大規模なデータ分析に基づいた研究結果ということで、説得力がありますね。
2005年から2022年までの168カ国、243万人を対象とした分析では、インターネット利用と心理的ウェルビーイングの間に関連性は認められませんでした。
また、2000年から2019年までの204カ国における不安障害、うつ病、自傷行為の有病率データについても、インターネット利用との関連はほとんど認められませんでした。
この研究は、インターネット利用に対する従来の認識を覆すものですね。
インターネット利用の影響:更なる研究と考察
ネット利用は人生にどんな影響を与える?
満足度や効力感に影響
インターネット利用の影響については、更なる研究が必要ですね。

✅ 2021~2022年に入社した新入社員の75%がジョブ型雇用を歓迎し、希望する部署・職種で働けるかどうかが入社に影響すると回答しました。また、業務経験が不足しているためキャリア形成が描きづらいと感じている一方で、テレワークは仕事がしやすいと感じる一方、約60%が対面でのコミュニケーションを求めているという結果が出ています。
✅ Z世代の新入社員は挑戦よりも失敗を回避する傾向があり、考えが合わない上司とは距離を置く傾向が見られます。
✅ 仕事や職場への満足度が高い新入社員は、多くの支援者を獲得し、今後のキャリアの見通しを立てています。また、自己効力感・自己肯定感が高く、挑戦にも積極的であるという結果が出ています。
さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000082530.htmlネット上の対人関係が人生満足度や社会的効力感に影響を与えるというのは興味深いですね。
ただし、研究グループは、テクノロジー企業からのデータ提供が不足している現状を指摘し、インターネット利用の影響についての理解を深めるためには、より詳細なデータが必要であると主張しています。
一方、別の研究では、男子学生を対象としたパネル調査により、ネット使用がネット上の対人関係を通じて、人生満足度と社会的効力感に影響を与えることが明らかになりました。
同期ツール使用は、ネット上の異性友人との関係が人生満足度を高める一方で、直接的な負の影響を与える可能性も示されました。
また、同期・非同期ツールはそれぞれ異なる形で、ネット上の対人関係を通じて社会的効力感を高める効果があることもわかりました。
同期ツールと非同期ツールがそれぞれ異なる影響を与えるというのは、興味深いですね。
本記事では、インターネット利用とメンタルヘルスの関係について、最新の研究結果を紹介しました。
💡 インターネット利用は、必ずしもメンタルヘルスに悪影響を与えないことが明らかになりました
💡 今後の研究で、インターネット利用とメンタルヘルスの関係について、より深い理解が得られることを期待しています。
💡 デジタルウェルビーイングを意識し、健康的なデジタルライフを送ることが重要です。


